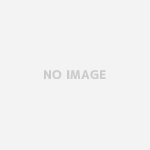プロフィール
ニックネーム SILVA
声帯学研究者
音楽は好きで、軽く唄ったり聞いてはいたものの、実際にヴォーカルトレーニングをしようとしたのは、10代後半からです。特に、ハードロックやメタル系の音楽に影響を受けて、それらのヴォーカルスタイルのレベルの高さに感銘を受けました。結果、どうにかして、このような能力をトレーニングによって、習得できないものかと、客観的に、自分自身や時には、他人を実験台に使い、データを収集してきました。自分では習慣的に行っているため、トレーニングという感覚はありませんでしたが、客観的にみたら、これはトレーニングにもなるなということで、このブログで説は明するためにトレーニングという言葉を使っています。
特に、トレーニングをしていて、自分が進化すればするほど、他人の歌唱スタイルの理解が進み、上手い歌手と下手糞な歌手の区別がはっきりしました。このブログでは、できる限り、大衆にインパクトのあるヴォーカリストを目指せるようなポイントを掲載していきますので、もしよければ読んでみてください。
サイトマップ
特に、このWEBのサイトの大きなトピックとして、下記の3つの内容について公開いたします。
[高音の出し方 編] …特に、発声の方法論ではなく、自己分析できる能力を徹底します。
[カラオケの達人 編] …まずはどのようにすれば、正しい発声を行うことができるのかを体感してもらいます。
[プロになる 編] …自分の個性の追求などに役立つような内容。
その他には、[HOME]のブログコーナーでは、日々の出来事などについて更新しています。
ひとこと
私自身が、この10年以上で発声トレーニングを試行錯誤で試して、確信していることが、高音を出すというイメージが初期と大きく変わったことです。特に、はじめた頃は、どうしても高音の音になると、苦しい。しかし、出ているからOKのような感じで、力まかせで出そうとするので、何曲も歌唱していけば、当然、声が出にくくなっていく。その結果、喉を壊すことになる。しかし、今では、高音が出るのは当たり前で、苦しいとかいった感覚はまったくなくなった。また、高音の声質に関しては、地声のような響きで安定のある声質を出せるようになった。たとえ高音を連発するフレーズがあったも、まったく崩れることなく、むしろ喉に損傷もない。おそらく、この出し方の感覚は、はじめからできる人もいれば、一生たどりつかな人もいることだろうと思う。
私自身は、トレーニングを我流で始めた頃は、裏声とよばれる音域は、hiF#まで、出すことができた。また地声のブレイクポイントがG#で、それ以降のhiA#からの音は、裏声と地声が混じったようなハイブリットな音で出すことができたが、この部分の音域が、不安定で、力みすぎで、何曲も歌唱していくと、喉周辺の筋肉がつかれ、声帯が損傷し、声がかすれる結果となった。当初の頃から、伸びやかに唄っている高音域のロック歌手などとの違いは、どこにあるのか? それを見つけて自分のトレーニングに反映させるのが課題でした。プロとよばれる歌手でも、同じ人間で、声帯の構造も音質がしがうだけで、たいした差はないはずです。となると、使い方に違いがあり、まさにその部分を正しいやり方に変えてやれば、高音は誰にでもでると確信していました。プロの歌手といっても、うまいと思えるひとだけに絞って参考にしています。彼にらに共通する点は、みんな、楽に歌っているということです。つまり、自然に音をだしている。私は、その部分にだけ焦点を絞って、試行錯誤でトレーニングを考えて、自分がそれを行うことで、音域が広がり、これまで、苦しかった部分が標準的に使えるようになりました。当然音域が広がったからといって、全ての音域が使い物になる音域ではありません。ただ、どんな状況でも確実に出せる自信をもつことにもつながり、今では、音域がどうこうなんいうことはどうでもよく、自分の一番良い響きのポイントをさらに磨くことにトレーニングの目的を変更しています。
では、高音域の開発トレーニングとは、どんなものか? 一言で言うなら、ファルセットを高音から低音まで鍛える。ただこれだけなんです。これがありえないほどの効果があり、今、書籍などで、ミックスボイスがどうこういっていうようなものがあるが、あくまで参考としてで知っておけばよいことで、結局自分の喉の感覚は自分にしかわからない。そこからは、自分で分析的に、試行錯誤で感覚を磨いていくしかないのがボーカルのトレーニングです。それらのポイントだけをこのブログでできるかぎり紹介したいと思います。ただ、それらを生かすも殺すも自分次第ですので、自分自身の体感を分析的に把握して、トレーニングしてください。